 |
| 民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第3回は「取得時効」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
| 追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
| 第3回 「取得時効」 ずっと自分の物として持っていると、 自分の物になるんです。。。 |
| Aが,Bの土地を不法に占有して20年経てば、その土地はAのものになる。これが取得時効だ。他人の物でも所有者のつもりになって(「所有の意思」で)、平穏・公然に20年間占有すれば、その物の所有権を取得するのだ。なお、Aが占有を開始した時に、その物が自分のものだと過失なく信じていたとき(善意・無過失)なら10年でよい。たとえば、Bからその土地を買ったのだが実はBのものではなかったというようなときにはこのようなことが起きうる。 |
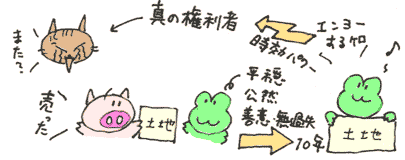 |
|
ここがよく出る ■この20年(又は10年)が過ぎる前に、BがAに返せと請求したり、AがBに「あなたの土地です」と認めたりすれば、本当はBのものではないということが明らかになるから、時効は中断する。中断するとそれまでの時効期間は水の泡になる。中断行為が終了すると、時効は振り出しに戻ってまた一から進行を始める。 ■物の占有を失ったときも時効は中断する。 ■20年(又は10年)経った後でも、Bが返せと請求してきたのに対して、Aが「もう時効だ」と言わなければ、時効の恩恵は受けられない。これを援用という。時効の効果を受けるのには援用が必要なのだ。 ■Aが時効の利益を受けたくなければ、これを放棄することもできる。放棄をすれば、援用はできなくなる。なお、この放棄は、時効期間が経過する前にあらかじめしておくことはできない。時効が完成した後にすべきものだ。 ■時効が完成すれば、20年(又は10年)前から、ずっとAのものだったことになる。時効が完成した時から将来に向かってAのものになるのではない。 |
| ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
|
次回は 「177条」です。ご期待ください。 |
Copyright (C)2009 SEMINET, KNoT All rights reserved. |
||