 |
| 民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第9回は「債権者代位権」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
| 追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
| 第9回 「債権者代位権」 債権者は債務者の財産減少を食い止めることもできます。。。 |
| AはBに100万円を貸しているが、Bにはこれを返済するめどがたっていない。それにもかかわらず、BはCに貸している100万円を取り立てないでいる。このような場合、債権者AはBに代わってCから取り立てることができる。これが、債権者代位権だ。この場合、Aのもっている債権を被保全債権と呼ぶ。また、Cのことを第三債務者と呼ぶ。 よく考えると、Bが借金の取り立てを放っておくのも自由なはず。しかし、放っておけば時効にもなるし、Bの財産的利益は減少してしまう。民法はBの財産が減って困る債権者に、債務者の財産管理にチョッカイを出す権利を与えたのだ。 | |
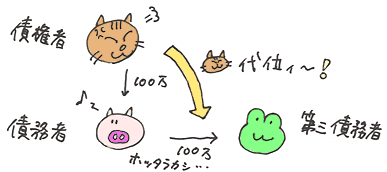 |
|
| ここがよく出る | |
| ■ | 債権者代位権を使うには、Bが無資力(借金が財産を上回っている状態)であることが必要だ。Bに借金を返す余裕があるときにまで債権者が介入するのは余計なお節介になるからだ。なお、これには例外があることに注意(債権者代位権の転用事例と呼ばれている)。 |
| ■ | 債権者は、代理人として行動するのではない。自分の名で他人の権利を行使する資格が与えられるのだ。 |
| ■ | 債務者の意思をどこまでも尊重すべき権利(一身専属権という)は代位して行使することはできない。 |
| ■ | 債権者代位権を行使するには、原則として、被保全債権の弁済期が到来していることが必要だ。しかし、例外として、保存行為の場合(たとえば、BのCに対する債権が時効にかかりそうなときに時効を中断するためにCに請求をする)と、裁判上の代位の場合(裁判所の許可を得て行う場合)には、弁済期が到来していなくてもよい。 |
| ■ | 債権者は、直接自分に引き渡せと請求してよい(Bが受け取らないと困るから)。ただし、Bの権利がB名義に登記をせよというものの場合は、A名義に登記をさせることはできない(Bが拒んでもB名義に登記させることが可能だから)。 |
| ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
|
次回は 「保証人」です。ご期待ください。 |
Copyright (C)2009 SEMINET, KNoT All rights reserved. |
||